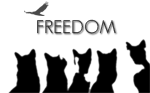(たかぎ じんざぶろう、1938年7月18日 - 2000年10月8日)は、日本の物理学者、専門は核化学。理学博士(東京大学)。 原子力発電の持続不可能性、プルトニウムの危険性などについて、専門家の立場から警告を発し続けた。特に、地震の際の原発の危険性を予見し地震時の対策の必要性を訴えたほか、脱原発を唱え、脱原子力運動を象徴する人物でもあった。原子力発電に対する不安、関心が高まった1980年代末には、新聞、テレビ等での発言も多かった。 1995年、『核施設と非常事態 ―― 地震対策の検証を中心に ――』を、「日本物理学会誌」に寄稿。「地震」とともに、「津波」に襲われた際の「原子力災害」を予見。「地震によって長期間外部との連絡や外部からの電力や水の供給が断たれた場合には、大事故に発展」するとして、早急な対策を訴えた。 福島第一原発 について、老朽化により耐震性が劣化している「老朽化原発」であり、「廃炉」に向けた議論が必要な時期に来ていると (1995年の時点で)指摘。 加えて、福島浜通りの「集中立地」についても、「大きな地震が直撃した場合など、どう対処したらよいのか、想像を絶する」と 、その危険に警鐘を鳴らしていた。 |
〈ニッポン人脈記〉石をうがつ:15(2012年9月25日朝日新聞) 炉水を分析すると放射線汚染の数値が予想以上に高い。基礎的な研究をもっと重ねるべきだと訴えたが、会社はそれを喜ばなかった。高木は会社を去り、東大原子核研究所を経て、30歳で都立大の助教授に迎えられた。高木は子どものころ、元士族の祖母から武士教育を受けた。 懐刀を前に「志と異なることがあれば切腹してでも節を守れ」と教えられた。7歳の時に日本は戦争に負けた。潔く切腹すると思っていた軍人たちはそれをせず、軍国教育を進めた学校の先生の言動は一変した。「自分で考え、自分の行動に責任をもたなくては」。幼心に、そう思った。高木のもう一つの原点は、都立大に移ってから通った三里塚だ。農民たちの抵抗もむなしく、農地はブルドーザーで押しつぶされた。 自分の学問は彼らにとって何の意味があるだろうか。彼らと不安を共有するところから出発するしかない――。考えた末に35歳で大学を後にし、在野の科学者になる道を選ぶ。 著書にこう書いている。 「反原発というのは、何かに反対したいという欲求でなく、よりよく生きたいという意欲と希望の表現である」 その後、出版社の七つ森書館を起こした教え子の中里は、2000年の夏、高木に呼ばれた。大腸がんで病床にいた高木は「私がこれまで書いてきたものをまとめてほしい」と言った。高木はその年の10月8日、62歳でこの世を去る。中里は2年半かけて高木の著作集を出版した。 全12巻。そう売れるものではなく、会社は傾いたが、カンパで何とかしのいだ。「社会のために役に立たない下らないものは出したくない」。中里はその思いをいまも貫く。福島で起きた原発事故は、日々の暮らしを壊し、ふるさとを奪い、家族を引き裂いた。1年半がたった今も約16万人が県内外に避難する。 「しかたない」や「あきらめ」からは何も生まれてこない。あきらめずにやってみなきゃ。人々の心の中に希望の種をまき、一緒に助け合いながら育てていこう――。「未来は一人ひとりの選択と行動にかかっています」久仁子はそう言って、写真の中で笑う高木を見つめた。 |