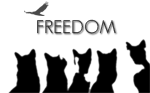「世の中、ウソだらけなのね。このまま、みんなで知らんぷりを続けちょったら、また同じ過ちを繰り返してしまう」 山が色づき始めた山口県柳井市。花街のたたずまいを残す旧市街地の古びたアパートで、福島菊次郎さん(92)が憤る。男二人で語り明かした4日間。話題は、福島原発から写真家としての出発点となった被爆地・広島の記憶に転じ、特定秘密保護法案や憲法改正の動きに及んだ。「胃と前立腺はがんにやられ、目と耳と足腰は期限切れ」と言うものの、反骨精神は衰えを知らなかった。1921(大正10)年、同県下松(くだまつ)市の小さな漁村の網元の四男に生まれた。今では希少となった「社会派の報道写真家」の先達である。その風貌もさることながら、一徹なる生きざまは、立ちはだかる巨大な風車に、やり一本で挑んでいったドン・キホーテをほうふつとさせる。被爆者、安保、東大紛争、三里塚、水俣……。戦後史を彩る現場に常に身を置き、カメラを「武器」に「権力のうそ」を暴き続けた。駆り立てたのは、「忠君愛国」の名のもとに人々を死に追いやった皇国への怒りと、それを妄信してきたことへの自責の念だ。 時代は経済成長期へと突き進み、報道写真の需要も激減した。「モノと金に浮かれる国と人々」に絶望し、東京から瀬戸内の海を望む故郷の山口に戻ったのは82年。61歳で、自給自足の隠とん生活を志した。一度は表舞台から退いた福島さんが、90歳の誕生月を迎えた2011年3月の東日本大震災を機に、再び腰を上げた。同年秋、福島原発周辺の被災地に入り確信する。「国民の命と大地を奪ったのに、誰も責任を取ろうとしない。じゃったら、僕もまだくたばるわけにはいかん。なれ合いの日本社会に、一石を投じたい」。カメラをワープロに替え、老眼鏡を2枚重ねで思いを記す。年金も受け取らずに、愛犬ロクと暮らす。「お上にあらがう以上、世話にはならん」。92歳のジャーナリストの気概である。【萩尾信也】=つづく http://mainichi.jp/shimen/news/ 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/2 玉砕覚悟の軍国少年(毎日新聞 2013年11月07日 東京朝刊) 広島西部第10部隊に入隊し、弾薬や物資を馬で運ぶ部隊に配属された。厳しいしごきに耐えかねて逃走した新兵が、井戸から遺体で引き上げられ、上官が「この非国民め」と足蹴(あしげ)にした。人生はどう転ぶか分からない。福島さんは訓練中に馬に蹴られて骨折し、除隊になった。入院中に船で沖縄に向かった部隊は、魚雷で海に消えた。「自分だけ生き残ったことが、恥ずかしゅうてならんかった」。当時の偽らざる心境だ。翌45年春、広島の部隊に再び召集された。戦局は悪化の一途。 ボロボロの軍服にぞうり履き、銃の支給などなかった。7月30日夜、部隊は予告もなしに貨車に詰め込まれ、翌日の昼に宮崎県の日南海岸で降ろされた。「本土決戦では、戦車に飛び込み玉砕せよ」。砂浜に10メートル間隔で穴を掘って中に入り、爆雷を背負ったまま息を殺して身を潜め続けた。8月15日の玉音放送は、松の木に下げたラジオから流れてきた。雑音の間に聞こえる「大元帥」の抑揚のない声に、激しい虚脱感に襲われた。抜けるように青い「敗戦の日の空」を記憶する。玉砕を覚悟した福島さんらは生き残り、原隊のある広島の街は「新型爆弾」で焦土と化していた……。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/3 被爆者の苦悩を撮影(毎日新聞 2013年11月08日 東京朝刊) 24歳の福島菊次郎さんが、人目を避けるようにして故郷山口に復員したのは1945年8月末の蒸し暑い夜だった。「原爆で死んだもんと思うちょった」。母親は涙を浮かべてすがりついてきた。幼なじみの半分は戦地から戻らず、友達の母親に「うちの子が生きておったら」と泣かれるのがつらかった。駅前で時計店を開き、時計の修理と写真の現像を始めた。 見合いをし、その年の暮れに結婚。仕入れのために汽車で広島の闇市に向かい、荒涼たる焦土にぼうぜんと立ち尽くした。翌春、後に「原爆ドーム」と名付けられる建物に草が生えたという新聞記事に目を留めた。カメラをカバンに入れて、忍ぶように撮影に行った。少年時代にいとこからお古のカメラをもらい、写真には興味があった。同じころ、民生委員を引き受けた。被爆者らの苦境を目の当たりにして、救援物資を集めるために写真展を企画。仕事の間に被爆地を歩き、写真を撮影した。 52年夏、知人の紹介で被爆者の中村杉松さんに出会う。漁師の中村さんは、動員先の広島市内で作業中に閃光(せんこう)を浴びた。赤子を含む10人家族。病床の夫に代わり、妻が行商で生活を支えていたが、51年にがんで急逝した。妻も被爆者だった。米軍に「研究用に献体を」と持ちかけられ、謝金で葬式を出した。老いた両親は「口減らしに」と家を出て、ほどなく子供2人も養子に出た。福島さんは米を差し入れ、生活保護の手続きを手助けした。 「正直、写真を撮りたいという下心もあった。でも、極貧の生活と病で七転八倒する姿に到底カメラを向けることはできんかった」。福島さんの述懐だ。そして、2年近く通ったある日−−。中村さんが畳に頭をこすりつけるように懇願した。「ピカにやられてこのざまじゃ。死んでも死に切れん。あんたが代わりに敵を討ってくれ。写真を撮って世界の人に知らせてくれ」悪寒に歯を鳴らしながら、「頭が割れる」と布団を転げ回る中村さんにカメラを向けて、福島さんは最初のシャッターを押した。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/4 僕には写真しかない(毎日新聞 2013年11月09日 東京朝刊) カメラとペンは、時に心を切り裂く刀になる。福島菊次郎さん(92)の写真家人生は、葛藤の中から始まった。「オレの代わりに敵(かたき)を討ってくれ」。被爆者の中村杉松さんの叫びに最初のシャッターを押して以来、福島さんはせきを切ったように写真を撮り続けた。中村さんの発作は突然始まった。「体がちぎれる」と全身をけいれんさせ、治まると糊口(ここう)をしのぐために漁に出て、生気を使い果たして家に担ぎ込まれた。 裸電球の6畳間に暮らす赤貧の父子。断末魔の声を上げる父親の傍らで、雑炊をすする子供たちにもカメラを向けた。中村さんの内股には、数えきれぬほどの傷痕もあった。亡き妻の後を追おうとカミソリで切り、その後も病苦から逃れようと刃を当てた。「こんなもの撮ったら、気が狂うたと思われる」。渋る中村さんに「本当の苦しみを撮りたい」と執拗(しつよう)に食い下がり、またシャッターを押した。 他の被爆者にもカメラを向けた。顔にケロイドがある被爆女性と交流を重ね、「写真を撮らせてください」と言って胸ぐらをつかまれた。「あなたは知ってるはずよ。私を見ると子供が火がついたように泣き、襲う男もいないことを」。彼女の叫び声は、今も胸に突き刺さったままだ。60年夏。福島さんは、中村さんと一家の軌跡を写真集「ピカドン ある原爆被災者の記録」にまとめて出版した。被爆者の苦境に肉薄した写真への反響は大きく、「日本写真批評家協会賞特別賞」を受賞したが、大きな代償も伴った。 カメラを向け続けることに耐えきれず、心が折れて幻聴や幻覚に襲われた。「精神衰弱」と診断され、精神科病院に3カ月入院した。気がつけば時計屋の経営も傾き、夫婦関係も崩壊していた。翌61年、福島さんは育ち盛りの3人の子供を連れて上京する。「一度は捨てようとまで思ったカメラの道じゃったけど、突き詰めて考えれば、僕にはやっぱりプロの写真家を目指すしか道がなかった」退路を断って、40歳の転身だった。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/5 現場が学校だった(毎日新聞 2013年11月12日 東京朝刊) 「現場が僕の学校だった」。福島菊次郎さん(92)の思いである。不惑でプロを志し、子連れで上京。企業広報のアルバイトや質屋通いで食いつなぐ時期もあったが、時代が報道写真を求めていた。高度経済成長期に突入した1960年代は、反戦市民運動も高揚した。硬派の総合誌が隆盛期を迎え、数年後には福島さんの写真も載るようになった。学生運動は瞬く間に全国に広がり、福島さんは最前線で目を見張った。「僕たち戦中派はお上に抵抗なんて考えられず、国のいいなりに戦地に送られて死んだ。だけど、学生たちは恐れることもなく権力に刃向かっていった。僕はその姿に感動して、カメラを向けた」 戦争が終わっても、国家や権力の理不尽な仕打ちは続いていた。 66年、国際新空港の建設地が千葉県・三里塚に決まった。戦後に入植し、苦労して荒れ地を開墾した農民たちは、不意打ちの決定に立ち上がった。収用地に砦(とりで)を築き、地下壕(ごう)を掘って、老人決死隊や少年行動隊を結成して抵抗した。5年後の2月下旬に行政代執行が始まり、翌月5日に3500人の機動隊が突入した。農民と支援する学生や市民は、投石や竹やりで反撃した。機動隊員に「おれは地権者だ」とつかみかかる老人、立ち木に体を縛り付けて抵抗する女性たちもいた。騒然とする中で、農民放送塔から流れてきた「故郷(ふるさと)」の旋律は忘れない。一瞬、怒号がやみ、あちこちからおえつが漏れて大合唱になった。 ♪うさぎ追いしかの山 小鮒(こぶな)釣りしかの川♪ その歌声を引き裂くようにチェーンソーがうなり、地響きを立てて放送塔が倒された……。 原爆や在日の取材では差別と向き合い、公害や環境破壊の現場では人間の罪深さに憤った。市民運動やウーマンリブには生き方を学んだ。身を挺(てい)しての取材が続いたが、子供のために守ったことがある。家事をできるだけやり、緊迫した現場からの帰りには家の前で立ち止まり、深呼吸をした。そして怒りやいらだちを外に置いて、玄関を開けた。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/6 隠し撮り、権力告発(毎日新聞 2013年11月13日 東京朝刊) 「特定秘密保護法があれば、僕は逮捕されちょったろう」。法案を審議するテレビの国会中継を横目に、福島菊次郎さん(92)が言った。「権力のウソ」を暴くためなら、だまし討ちや隠し撮りもいとわなかった。カメラの矛先は、「戦争放棄」や「戦力不保持」を掲げる憲法を骨抜きにしていく国に向けた。安保闘争で憲法論議が盛り上がった1969年、福島さんは言葉巧みに防衛庁(当時)に売り込みを図った。 「学生運動を取材して、これでは日本も末だと思いました。でも、自衛隊の若者はまじめに国を守っている。僕はそんな姿を撮影したい」ほどなく、掲載前にチェックを受けるのを条件に幹部候補生学校の撮影を許可された。そんな写真を雑誌に発表しながら隊内の取材先を広げた。 「次は武器製造の現場も見たい」。打診すると企業に話を付けてくれた。機関銃に戦車に戦闘機。ただし、製造過程は撮影禁止だらけで、防衛庁の監視が付いた。福島さんは、それをこっそり撮影した。「ファインダーを見ずに手撮りする練習をして、騒音に紛れてシャッターを押した」翌70年、それを無断で雑誌に掲載した。タイトルは「迫る危機 自衛隊と兵器産業を告発する」。掲載前に広報課長に呼び出され、原稿の青焼きを突きつけられて罵倒された。「貴様、だましたな。掲載を止めろ」 この時、福島さんは開き直っている。「あなた方こそ、憲法違反で国民をだましちょる。とやかく言う資格はない」 しばらくして原稿を入れた袋を持って夜道を歩いていたら、自宅近くで暴漢に襲われた。「そんなもん持ちやがって」。刃物で切りつけられ、鼻骨を折って10針縫う大けがをした。1カ月後、今度は不審火で自宅が焼けた。家に保管していたネガは、高校生の長女が間一髪で持ち出して助かった。当時、福島さんは子供たちにこう告げている。「もし、お父さんに何かがあったら、必ず弁護士さんに電話をして、遺体を解剖してもらうように」=つづく http://mainichi.jp/shimen/news 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/7 還暦機に自給自足(毎日新聞 2013年11月14日 東京朝刊) 1970年安保を経てベトナム戦争も終結に向かうと、学生や市民の反体制運動は急速に衰退して、「三無主義(無気力・無関心・無責任)」という流行語が登場した。被爆者らが住んでいた広島の「原爆スラム」も撤去が進み、緑地化されていった。75年、初の訪米を終えた昭和天皇は記者会見で、戦没者を悼む気持ちを示しつつ、戦争責任の質問に「そういう問題についてはお答えができかねます」と述べた。戦争の記憶が風化してしまうことを福島菊次郎さんは危惧した。72年に沖縄返還がようやく実現。だが、日米間で「有事の際の核持ち込み」の密約が結ばれ、「非核三原則」は国民の知らぬ間にほごになっていた。 福島さんは時代の風にあらがうように取材を続けたが、硬派の報道写真を求める媒体は減少していった。「都合の悪いことはみんなで知らんぷりをして、モノと金まみれで生きる時代になった」還暦を越えた82年、成人した子供たちの自立を機に一念発起。カメラを置いて、自給自足の隠とん生活を目指して故郷山口に移り住む。 かつては豊かな海と白砂青松に恵まれた故郷は一変、臨海工業地帯の排水で海は汚染され、近隣の島では原発の建設計画が浮上していた。小さな無人島を借りて、自らの手で小屋を建て、畑を開墾した。30歳年下の女性と暮らしたのもこの時代だった。「体調を崩して無人島への移住をあきらめ、失意の中で自殺を図ったこともあるが、島の日々は懐かしい思い出になった」。今に至る思いである。 87年、集団検診で胃がんが見付かる。死を覚悟して撮りためた膨大な写真を整理し、書き下ろしの原稿を加えて「戦争がはじまる」と「瀬戸内離島物語」という2冊の写真集を出版した。88年秋、胃の3分の2を手術で切除。体重が10キロ減の39キロに落ちて、腹に20センチの傷痕が残った。 ほどなく、入院先のテレビに昭和天皇の顔がアップになって、「下血報道」が始まった。それが「昭和の終わり」への序章だった。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/8 戦争責任、問い続け(毎日新聞 2013年11月15日 東京朝刊) 「昭和の終章」は1988年、福島菊次郎さんが67歳の秋に始まった。 山口県柳井市の病院で胃がんの手術を受け、長期の入院生活に気弱になった時期だった。突然、備え付けのテレビに臨時ニュースが流れ、昭和天皇の容体悪化を報じた。「このまま昭和が終わってたまるか」。怒りが生気を呼び起こした。思いを伝える手段は、長年撮りためた写真だった。被爆者、遺族、戦争孤児、中国残留孤児……。年末に退院し、病み上がりの体にむち打って暗室にこもり、写真を焼いて250点のパネルを作製した。年明けの1月7日、昭和天皇が亡くなり、世の中は「自粛」に染まったが、「戦争責任展」と銘打ってパネルを無料で貸し出したら、全国各地から声がかかった。 妨害も相次ぎ、中止にもなった。東京都杉並区では爆竹が破裂し、パネルに消火液がかけられた。写真をナイフで切られた会場もあった。栃木県小山市では会場に銃弾が撃ち込まれた。「天誅(てんちゅう)を加えてやる」「夜道を歩くなよ」。脅迫電話も相次いだ。言論を力で封殺した過去の風景が重なった。それでも写真展は、全国169カ所で開催され、その後も「日本の戦後展」などと名を変えて続いている。 「日本の戦後は、ごまかしと取り繕いの積み重ねだった。体制を変えても、中身は変わらなかった。突き詰めれば、国民一人一人が過去と向き合おうとしなかったことに本質がある」。福島さんの思いである。柳井市にある現在のアパートに移り住んだのは99年。「僕に21世紀は似合わない」とベニヤ板で棺おけを手作りし、「遺言代わりに、写真に写らなかった戦後を文章で残そう」とワープロのキーボードをたたき始めた。2001年には、急性膵炎(すいえん)で入院。その後も大腸ポリープに前立腺がん、胆のう結石の摘出と続き、「満身創痍(そうい)の身」になったが、いつの間にか棺おけは部屋の隅に追いやられ、執筆のための資料や本が壁を埋め尽くしていった。=つづく 生きる物語:硬骨のドン・キホーテ/9止 原発事故、魂に再点火(毎日新聞 2013年11月16日 東京朝刊) 福島菊次郎さん、92歳。身長160センチ、体重36キロの体に、気骨あふれるジャーナリストである。 記者が山口県柳井市の家に初めてうかがったのは2007年。「美しい国づくり」を掲げた第1次安倍政権下、防衛相が「原爆しょうがない」発言で辞任した夏だった。 「お上が独り善がりの価値を国民に押しつけてるようじゃ、いつか来た道と同じだよ」。福島さんの憤りを記憶する。 以後、再会の度に先達の言葉に刺激を受けた。 「報道の中立性を掲げて安全地帯に逃げ込んでは、実像は見えない」 「現場に身を置き人と向き合わずに、心を動かす写真や記事はない」 そして当人は重たいカメラをワープロに替え、写真に写らなかった戦後を文字に記し、「ヒロシマの嘘」「菊次郎の海」「殺すな、殺されるな」の3冊を出版した。一線から退いたかに見えた福島さんのジャーナリスト魂に、再び火を付けたのは90歳になった11年3月、東日本大震災の福島原発事故だった。 「広島と同じ過ちが繰り返される」との思いにかられ、同年9月には、後輩のカメラマンらと福島に向かう。 放射能汚染で先祖伝来の大地と家を奪われた農民。孫子の体への影響や差別を懸念する両親……。広島で出会った被爆者の苦悩が重なった。そして13年秋、「強い国づくり」を掲げた第2次安倍政権下で、原発事故のデータ隠しやうそが発覚し、国内の原発再稼働の流れが止まらない。自宅を再訪すると、福島さんは机に向かっていた。 「僕もワープロも寿命スレスレで、ちゃんと動くかどうか最初に拝むことにしてるの」。スイッチを入れ、まずは手を合わせるらしい。「肝心なことは都合の悪いことや面倒なことから目をそらさず、自分で考えて、できることから始めること。僕はもう少し生きながらえて、ヒロシマとフクシマを結ぶ本を書いて抵抗したい」本棚にはベトナム戦争に抗議して焼身自殺を図った僧侶の写真が置いてあった。【萩尾信也】=おわり ============== ◇福島さんメモ 山口県柳井市在住の社会派の報道写真家。被爆者、学生運動、三里塚闘争、公害、原発、自衛隊や軍事産業を取材。 http://mainichi.jp/shimen/news/ |
「ヒロシマ」撮った90歳、最後の仕事は「フクシマ」(2011年12月9日朝日新聞) これまでに胃がんや前立腺がんを病み、体重は37キロ。その体で9月、約半世紀使い込んだニコンFなど2台のカメラを持ち、津波に押し流された墓石が集められた南相馬市を、何度も転びながら撮影した。福島さんと25年来の交流があり、被災地で取材を続ける写真家の山本宗補さん(58)が道案内をした。原発事故の後、牛を殺処分し、仲間を自殺で失った飯舘村の酪農家、長谷川健一さん(58)も訪ねた。「美しくすがすがしい山や森が、一転して放射能におびえる絶望的な光景になったことにショックを受けました」。全てを失っても、村の将来を真剣に考える姿に心を打たれた。 9月には、大江健三郎さんらが呼びかけ、主催者側発表で6万人が参加した東京での「さようなら原発集会」も取材。3日間で36枚撮り白黒フィルム30本を使い切り、疲労で地面にしゃがみ込んだ。福島を取材したのは、「日本は『安全・安心』だとうそを重ねて原発を造り、事故を起こした。広島の原爆慰霊碑に『過ちは繰返しませぬから』と刻みながら、朝鮮戦争やベトナム戦争に加担したことと僕の中で重なる。 ぜひ取材したいと思った」からという。1945年には広島の部隊に所属していたが、原爆投下直前に県外に移動し難を逃れた。翌年から広島に通い、61年に被爆者の闘病や貧苦を追った写真集「ピカドン」を出版。自衛隊や日本の兵器産業の内部に入り込み、その実態を明らかにする写真を雑誌に発表した。暴漢に襲われ、家が不審火で焼ける経験もした。 それでも取材をやめなかった。「あったことを隠してはいけない」と、より深く取材し、「不正を告発する」道を選んだという。「僕が写した戦後史から消えていった悲劇の人たちに比べれば、僕は飯を食い、子どもを大学に上げて、いわば無傷でいる」。そのことがトラウマになっているという。「今回の大震災でも、自分だけが生き残ったことを責め、苦しみを抱え込んでいる人が多いのではないでしょうか」 この取材を「写らなかった戦後4 ヒロシマからフクシマへ」にまとめ、逝きたいという。 そんな福島さんの姿を2年余り追った映画の制作も進む。「ニッポンの嘘〜報道写真家 福島菊次郎90歳〜」(仮題、ドキュメンタリージャパン)で、来年1月に完成の予定だ。(高波淳) 〈ニッポン人脈記〉石をうがつ:2(2012年9月3日朝日新聞) 菊次郎に尋ねられた那須は、こう答えた。「ウソが嫌いだから」東京生まれの那須は、早稲田大卒業後、結婚して山口に移った。高校教師をしている夫の友人らと話をしているうちに、上関原発の是非が論議になっていることを知る。 参加した勉強会では、原発内で現場監督を務めてきた男性の告白を聞いた。施設の点検や修理に当たる作業員は、ほとんどが専門技術をもたない地元の農民や漁師たち。線量計の警告音が鳴る中、慌てて作業を進めるのが日常茶飯事だったという。 那須は94年から島に通った。環境調査を強行する中国電力、町を二分した町長選、その中で続く暮らし。07年に出した写真集「中電さん、さようなら」は、日本自費出版文化賞で特別賞を受賞した。菊次郎の原点は、戦争にある。大戦末期に召集され、広島の隊へ。その後宮崎に派遣され、手榴弾(しゅりゅうだん)を抱えて米軍の上陸を待ちながら敗戦を迎えた。原隊は原爆で全滅した。「70年は草木も生えない」と言われた当時の広島。郷里の山口県下松市で時計店を営んでいた46年春、原爆ドームのがれきの間から芽がふいたという新聞記事を読み、無性に見たくなった。 事前に記事を見せるという約束を破り、軍備の拡張を批判するキャンペーンを雑誌で展開した。「だましたな」。当時の防衛庁から記事の撤回を要求されたが、菊次郎は言った。「ウソを言って撮影したのはわびるが、そっちこそ大ウソで国民をだましていないか」それからほどなく、路上で襲われた。前から来た男に殴られ、折れた鼻から血が噴き出した。不審火で自宅が全焼する目にも遭った。だが、菊次郎はシャッターを押し続けた。安保、ベトナム反戦運動、公害、ウーマンリブ――。駆けつけられなかったのは、三島由紀夫(みしま・ゆきお)の自殺ぐらいだった。菊次郎はいま山口に戻り、柳井市の1Kのアパートで愛犬のロクと暮らしている。 「てめいは生きながらえて、仕事も評価されて……」。戦争に無批判で加わったこと、そして生き残ったことへの罪悪感。それが、「償い」として反権力に向かわせてきた。菊次郎には、「ヒロシマ」と「フクシマ」が重なって見える。戦争に突き進み、軍都だったがゆえに標的になった広島。安全神話のなかで原発が建設されていった福島。過去を見つめ直さなければ、前には進めない。菊次郎は、自分の思いを文につづり、後の世に残したいと思っている。(大久保真紀) 福島 菊次郎(ふくしま きくじろう、1921年3月15日 - )は、日本の写真家、ジャーナリスト、ノンフィクション作家。 中近東、アラブ、ソビエト連邦などに長期にわたる取材もこなした。「ピカドン」の撮影では、被写体となった被爆者の凄惨な生活状況を間近に見続けたことで不眠症となり3カ月間入院。また「迫る危機」の撮影では、1年以上かけて防衛庁(当時)を信用させ、兵器工場内の取材を許されたが、撮影禁止箇所を隠し撮りして無断で公表した。その後、暴漢に襲われ重傷を負い、自宅を放火されている。 作品は、『中央公論』、『文藝春秋』、『朝日ジャーナル』などの総合雑誌グラビアで約3300点が発表されている。また、「写真で見る戦争責任展」などの写真展を全国510会場で開催した。 |