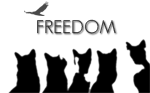| <佐伯 啓思> |
佐伯 啓思(さえき けいし、1949年12月31日 - )は、日本の経済学者、思想家。京都大学大学院人間・環境学研究科及び総合人間学部教授。共生文明学、現代文明論、現代社会論といった国際文明学、文明論を研究している。第4期文部科学省中央教育審議会委員を務めた。大きく分けて、米国批判と近代批判がある。自由主義や民主主義を国家の理念に据えるアメリカこそが、思想史的に進歩主義、革新主義であり、冷戦が終結した今、最も左翼的で進歩的な国家はアメリカであるとして、アメリカおよび自民党を保守・右翼とみなし、反米および反自民党を革新・左翼とみなすという誤謬に陥っている戦後の日本社会を批判している。 また、米国の庇護の下に繁栄を遂げた戦後日本には欺瞞があるとして、「アメリカニズム」への懐疑を表明している。経済思想面では、ケインズの立場に立脚し、グローバリズムおよび、構造改革、小泉・竹中の新自由主義・小さな政府路線を批判している。 ニーチェの思想に基づき、近代の価値観である基本的人権や自由主義、民主主義は必然的にニヒリズムに陥るとしている。先述のアメリカ批判もこの延長上にあり、日本がヨーロッパ−アメリカ化し、ニヒリズムに陥っていることを問題視している。かつてはニヒリズムに対抗する術として、師の西部邁同様、保守主義を標榜していた。 しかし、近年では、冷戦体制崩壊後の社会構造の変化によって、「保守と革新」、「右翼と左翼」という対立軸が不明瞭になったこともあり、これらの対立軸が既に時代遅れになった感があるとして、保守や革新に安易に拘泥することにも懐疑的な姿勢を向けている。現在では、社会思想史や経済思想および時事問題から日本思想史・日本哲学に軸足を移している。ニヒリズム超克の試みとして、東洋や日本の「無」の思想の意義を探り、小林秀雄や保田與重郎、西田幾多郎と京都学派の哲学に言及している。 http://ja.wikipedia.org/wiki/佐伯啓思 (異論のススメ)1968年は何を残したのか 欺瞞を直視する気風こそ 佐伯啓思(2018/05/11朝日新聞) 私は68年の4月に大学に入学し、7月には無期限ストで授業はなくなった。69年1月には東大の安田講堂での攻防があってバリケードは撤去され、授業が再開されたのは3月であった。これは「革命」などといえるものではなく、フランスでは学生の「反乱」を押さえつけたドゴール大統領は68年6月に総選挙を行い大勝した。日本でも、70年の大阪万博を前にした高度成長の頂点の時代である。人々は、アポロ宇宙船による月面着陸の方に歓声をあげていたし、政治的にいえば、佐藤政権による沖縄返還の方がはるかに重要な出来事だった。 私は、全共闘運動には参加もしなければ、さしたる共感ももっていなかった。それは、私がそもそも集団行動が嫌いだったこともあるが、まわりには、マルクスやら毛沢東から借用したあまりに粗雑な「理論」を、疑うこともなく生真面目に信奉しつつも、実際にはまるでピクニックにでも出かけるようにデモに参加する連中をずいぶん見ていたせいでもある。しかし、それでも私は、あるひとつの点において「全共闘的なもの」に共感するところがあった。それは、この運動が、どこか、戦後日本が抱えた欺瞞(ぎまん)、たとえば、日米安保体制に守られた平和国家という欺瞞、戦後民主主義を支えているエリート主義という欺瞞、合法的・平和的に弱者を支配する資本主義や民主主義の欺瞞、こうした欺瞞や偽善に対する反発を根底にもっていたからである。 だから、これらの欺瞞と戦うには、合法的手段ではありえない。暴力闘争しかないということになる。私が共感したのは、この暴力闘争への傾斜であったが、そんなものはうまくゆくはずもない。そして、事実、暴力は内向してあさま山荘事件や内ゲバへと至り、全共闘運動は終焉(しゅうえん)する。戦後日本の学生主体の新左翼は、こうして暴力主義の果てに崩壊する。これはほとんど必然的な成り行きのように私には思われた。 むしろ、私が衝撃を受けたのは、70年に生じた三島由紀夫の自衛隊乱入、割腹自殺事件の方であった。米製の憲法を理想として掲げて、米軍に国防を委ねる平和国家を作り、あの戦争を誤った侵略戦争と断じたあげくに、とてつもない経済成長のなかでカネの亡者と化した日本、こうした戦後日本の欺瞞を三島は攻撃し、一種の自爆テロを起こした。三島自身が述べていたように、三島由紀夫と全共闘の間には、深い部分で共鳴するものがあったのだが、全共闘はそれを正面から直視しようとはせず、三島はそれを演劇的な出し物へと変えてしまった。 そのころ、評論家の江藤淳が「『ごっこ』の世界の終ったとき」と題する評論を書き、全共闘の学生運動も、三島の私設軍隊(楯〈たて〉の会)もどちらも「ごっこ」だと論じていた。学生運動は「革命ごっこ」であり、三島は「軍隊ごっこ」である。どちらも現実に直面していない。真の問題は、日米関係であり、アメリカからの日本の自立である、というのである。確かに、フランスやアメリカと比較しても、日本の学生運動は、どうみても「革命ごっこ」というほかない。機動隊に見守られながら「市街戦ごっこ」をやっているようなものである。 三島の方はといえば、効果的な「ごっこ」を意図的に演出していたのである。 日本の左翼主義は、その後、急速に力を失ってゆくが、私には、それは、多くの人が感じていた戦後日本のもつ根本的な欺瞞を直視して、それを論議の俎上(そじょう)にあげることができなかったからではないか、と思う。沖縄返還問題にせよベトナム戦争問題にせよ、その根本にあるものは、米軍(日米安保体制)によって日本の平和も高度成長も可能になっている、という事実であった。そのおかげで、日本は「冷戦」という冷たい現実から目を背けることができただけである。 この欺瞞が、利己心や金銭的貪欲(どんよく)さ、責任感の喪失、道義心の欠如、といった戦後日本人の精神的な退嬰(たいえい)をもたらしている、というのが三島の主張であった。三島は、あるところでこんなことを述べている。全共闘の諸君の言っていることは実に簡単なことだ。それは、国から金をもらっている大学教授が、得々として国の批判ばかりしているのはおかしいということだ、と。 もちろん、三島は、国立大学の教授は国家批判をしてはならない、などといったわけではない。精神の道義を問うたのであり、この道義を戦後日本は失ったのではないか、と問うたのだ。フランスの68年は、それでもポストモダンといわれる思想を生み出したが、日本は何も生み出さなかった。 そして左翼主義は、その後、ただただ「平和憲法と民主主義を守れ」に回収されてしまった。私は68年をさほど評価しないが、それでも今日の大学や学生文化にはないものが当時はあった。それは、社会的な権威や商業主義からは距離をとり、既成のものをまずは疑い、自分の頭で考え、他人と議論をするというような風潮である。その自由と批判の気風こそがかけがえのない大学の文化なのである。 (異論のススメ)保守とは何か 奇っ怪、米重視で色分け 佐伯啓思(2016/10/07朝日新聞) 同じ自民党でも、先日亡くなった加藤紘一氏はリベラルだとされる。それでわれわれはつい何かを理解したつもりになってしまう。しかし、今日の日本にはリベラルはおろか、保守という確かな思想が存在しているのだろうか。 * そもそも「保守」とは何か。今日の日本では、「保守」が政治的権力を掌握し、これに対して、「リベラル」がその対抗勢力であるかのように語られる。しかし、もともとは、「保守」の側が抵抗勢力であった。フランス革命が生み出した自由、平等、人権などの普遍性を唱え、それを政治的に実現すべく市民革命によって権力を掌握した革命派がリベラル(左翼)であり、それに抵抗して、伝統的社会秩序や伝統的価値観を重視したのが保守である。イギリスの政治家であったエドマンド・バークが保守思想の父と呼ばれるのは、彼が、フランス革命が掲げた革命的な社会変革や人権などの抽象的理念の普遍性を批判したからである。 改革は漸進的で、その社会の歴史的構造に即したものでなければならない、と彼は述べた。なぜならば、人間は既存の権威を全面的に否定して、白紙の上にまったく新しい秩序をうみだすことなどできないからである。人間の理性的能力には限界がある。それを補うものは、歴史のなかで作り上げられた慣習的秩序や伝統の尊重である、という。これが本来の保守であり、今でもイギリスに強く根を張っている。 ところが、近代社会は、系譜的にいえば、フランス革命の革命派の流れの上に成立した。つまり、自由、平等、民主主義、人権主義などの普遍性こそが近代社会の基本理念になってしまった。これをリベラルというなら、近代社会はリベラルな価値によって組み立てられている。「保守」はいわばリベラルの暴走をいさめる役割を与えられたのだ。 ところが話が混沌(こんとん)としてくるのは、アメリカが現代世界の中心に躍り出てきたからである。いうまでもなく、アメリカは王制というイギリスの政治構造や伝統的価値を否定して革命国家を作り出した。「独立宣言」にもあるように、その建国の理念は、個人の自由や平等や幸福の追求の権利をうたっている。 その結果、もしもアメリカの建国の精神という「伝統」に戻るなら、そこには、個人の自由、平等、民主主義など「リベラル」な価値が見いだされることになる。かりに伝統への回帰を「保守」というならば、アメリカの「保守」とは、自律した個人、自由主義、民主主義、立憲主義などへ立ち戻ることである。 ここに宗教的・道徳的価値を付け加えればよい。これに対して、「リベラル」は、20世紀の多様な移民社会化のなかで、文化的多様性と少数派の権利を実現するようなひとつの共同社会としてのアメリカを構想する。ここに、イギリスなどとは異なったアメリカ型の「保守」と「リベラル」の対立が生まれたのである。 ということは、本来のヨーロッパの「保守」からすれば、アメリカは自由、民主主義という普遍的理念の実現を目指す「進歩主義」の国というほかない。伝統を破棄して革新的な実験に挑むことが「進歩」だとする意識がアメリカには強い。こうした進歩主義を警戒するのが「保守」だというなら、アメリカには本来の意味での「保守」はきわめて希薄なのである。 * さて、それでは日本はどうなのか。われわれは、アメリカとの同盟を重視し価値観を共有する者を「保守派」だという。安倍首相が「保守」なのは、まさしくアメリカとの同盟重視だからだ。するとどうなるか。アメリカと協調して自由や民主主義の世界化を進め、たえざる技術革新によって社会構造を変革することが「保守」ということになる。これはまったく奇怪な話であろう。構造改革にせよ、第4次産業革命にせよ、急進的改革を説くのが「保守」だというのだ。もともと既成秩序の破壊、習慣や伝統的な価値の破壊を説き、合理的な実験によって社会を進歩させるという革新主義は「リベラル」の側から始まったはずなのである。 それが「保守」へと移ってしまい、リベラルは保守に吸収されてしまった。私は、「保守」の本質は、近代社会が陥りがちな、急激な変革や合理主義への抵抗にある、と思う。それは、社会秩序を、抽象的な普遍的価値に合わせて急激に変革するのではなく、われわれの慣れ親しんだ生活への愛着を大事にし、育ってきた文化や国の在り方を急激には変えない、という精神的態度だと思う。そして、この「本来の保守」の姿が今の日本ではみあたらないのである。蓮舫氏のように「バリバリの保守だ」といっている場合ではない。今日の日本に本当に必要なのは、「本当の」保守なのだ。 (異論のススメ)スポーツと民主主義 「停泊地」失った現代世界 佐伯啓思(2016/08/04朝日新聞) どうみても、あまり褒められた意味ではなさそうである。事実、英語の「スポート」にも「気晴らし」や「悪ふざけ」といった意味があり、これなどまさしく語源をとどめている。その「スポーツ」の祭典が6日からリオで始まる。ロシア選手の組織的なドーピング問題や、大会会期中、不測の事態に要注意などといわれる今回のオリンピックをみていると、ついその語源を思い起こしてしまう。ロシアのドーピングなど、はめがはずれたのか、たががはずれたのか、確かに停泊すべき港からはずれてしまった。 ところで、スペインの哲学者であるオルテガが「国家のスポーツ的起源」という評論のなかで、国家の起源を獲物や褒美を獲得する若者集団の争いに求めている。その様式化されたものが争いあう競技としてのスポーツであるとすれば、確かに、ここにもスポーツの起源と語源の重なりを想像することは容易であろう。 * いうまでもなくオリンピックは古代ギリシャ起源であり、ギリシャ人はスポーツを重んじた。争いを様式化し、競技を美的なものにまで高めようとした。そしてギリシャでは「競技」が賛美される一方で、ポリスでは「民主政治」が興隆した。民主主義とは、言論を通じる「競技」だったのである。 肉体を使う競技と言語を使う競技がポリスの舞台を飾ることになる。古代のギリシャ人を特徴づける特質のひとつはこの「競技的精神」なのである。スポーツと政治は切り離すべきだ、などとわれわれはいうが、もともとの精神においては両者は重なりあっていたのであろう。ということは、その起源(語源)に立ち返れば、両者とも一歩間違えば「はめをはずした不作法な行動」へと崩れかねない。競技で得られる報酬が大きければ大きいほど、ルールなど無視してはめをはずす誘惑は強まるだろう。 それを制御するものは、自己抑制であり、克己心しかなかろう。そのために、ギリシャでは、体育は、徳育、知育と並んで教育に組み込まれ、若者を鍛える重要な教科とみなされた。その三者を組み合わすことで、体育はただ肉体の鍛錬のみならず、精神の鍛錬でもあり、また、自律心や克己心の獲得の手段ともみなされたのであろう。その上で、運動する肉体を人間存在の「美」として彫像に刻印しようとした。問題は、言論競技としての民主主義の方で、むしろこちらの方が、成功したのかどうかあやしい。 民主主義の精神を鍛えるなどということは不可能に近いからである。ただわれわれが垣間見ることができるのは、ポリスのソフィストたちの「言論競技」のなかから、ソクラテスのような人物があらわれ、「哲学」を生み出したことである。しかしそのためにはソクラテスは「言論競技」を切り捨て、それを「言論問答」におきかえねばならなかった。彼は、政治よりも真の知識(哲学)を優位におき、それを教育の根本にしようとした。そうでもしなければ、スポーツも政治もただただ「はめをはずす」ことになりかねなかったからであろう。 * さて、これはギリシャの昔に終わったことなのであろうか。今日、われわれの眼前で展開されている事態をみれば、決してそうはいえまい。民主政治は、どこにおいても「言論競技」の様相を呈している。アメリカのトランプ大統領候補をドーピングぎりぎりなどといえば冗談が過ぎようが、この現象が「ディス・ポルト」へと急接近していることは疑いえまい。民主主義のたががはずれかけているのだ。スポーツに高い公正性や精神性(スポーツマンシップ)を要求するアメリカで、民主主義という政治的競技において高い精神性や公正性が失われつつあるのは、いったいどういうことであろうか。今日、オリンピック級のスポーツには、ほとんど職業的とでもいいたくなるほどの高度な専門性を求められる。そのためには、スポーツ選手は職業人顔負けのトレーニングを積まなければならない。これは肉体的鍛錬であるだけではなく、高度な精神的鍛錬でもある。 そこまでして、スポーツ選手は「ディス・ポルト」を防ぐ。しかし、政治の方には、そのような鍛錬はほとんど課されない。その結果、高度なスポーツは「素人」から遊離して一部の者の高度な技能職的なものへと変化し、一方、政治は「素人」へと急接近して即席の競技と化している。どちらも行き過ぎであろう。スポーツと民主主義を現代にまで送り届けたギリシャの遺産が、ロシアのドーピングやアメリカの大統領選挙に行きついたとすれば、現代世界は規律や精神の鍛錬の場である確かな「停泊地」を失ってしまったといわねばならない。 (人生の贈りもの)佐伯啓思(63):1(朝日新聞)
■英国に留学、欧州に根差す保守知る ――国のありようを考えた著書が多いですが、学問の出発点は政治学ではなく経済学ですね 高校のころに関心を持ったマルクスを勉強しようと経済学部を選んだものの、経済学の主流は「市場競争は結構なもの」という立場で、「人は合理的に行動し、個人の自由を確保し、生産性と効率を上げ成長する」という前提を問わない。そこが疑問だった。成長より環境重視でゆったり暮らす選択もあるし、個人の自由より共同体の安定を重く見る考え方もある。なぜ市場競争=善という価値判断がほかより勝るのか。どういう社会を作るのか、という展望が先にあるべきだと思った。アダム・スミスやケインズを価値や思想として理解したくて、40歳で在外研究の機会を得た時、留学先に英国を選びました。 ――英国で何を学びましたか ちょうどベルリンの壁が崩壊し欧州は大混乱で、英国はサッチャー政権末期。国際社会はドイツ統合を「民主化万歳!」と祝福しているのに、サッチャーは「欧州に生まれる強大な国への対処を真剣に考える」と発言した。国家間のバランス重視という欧州の政治の伝統を実感しました。 ――想像と違いましたか 市民革命が旧体制を潰し、「自由平等」「民主主義」の「近代」を実現した、という欧州は虚像でした。特に英国は大土地の所有権が今も貴族にあり、階級社会が温存されている。政治の中心は深い教養を求められるエリート。「金のために働くのは悪」というキリスト教的倫理も働く。ぶ厚い伝統が下地にあり、民主主義も極端な欲望追求に走らない。アメリカ経由で日本に入った薄く平板な「民主主義」と全く別物だった。この欧州の保守主義は、行って初めて実感できました。 ――日本で一般にイメージする「保守」とは違うんですね 移民国家の米国は、個人の自由や平等を共通の理念に国の建設に突き進んだ。共同体の伝統より、個人の開放や絶えざる経済成長が民主社会の実現と考える。日本はそんな米国流を受け入れた。特に戦後の日本は社会に連綿と続いた価値観を全否定し、個人の欲望追求に精を出した。その結果、人々はどこまでも満たされないことに疲れ、精神の豊かさを見失った。欲望民主主義の社会では、政治は利益誘導の票集めに傾き、どんな社会を目指すのかという展望を語ることもできません。過去の遺産の上に成り立つ精神、思考の土台に目を向けることが保守だ、と欧州で身をもって実感しました。(聞き手・織井優佳) ◇ さえき・けいし 1949年、奈良市生まれ。東京大経済学部卒。滋賀大助教授などを経て93年から京都大教授。「経済学の犯罪」「日本の宿命」など著書多数。 (人生の贈りもの)佐伯啓思(63):2(朝日新聞) ■大学でネクラ満喫 学問は自分で作る ――どんな学生時代でしたか ともかく東京に出たかったんです。エスカレーターというものにちゃんと乗ったのも、東京へ出てから。本屋が2軒しかない奈良の田舎を出たかったし、一人暮らしをしたかった。それで近すぎる京都でなく、東京大学に1968年4月入学しました。ところが学生運動が激しくなり、入学して2カ月で大学は無期閉鎖。友人はまだほとんどいない。ひたすら時間はある。街を歩いたり、デモの後ろにくっついてみたり。朝までやっている深夜喫茶でコーヒーを飲み、ケチャップで炒めたスパゲティを食べ、本を読み、数少ない友人と議論した。だから僕は、かなり経つまでスパゲティをゆでて食べるものとは知りませんでした。 ――がっかりですね いや、最高の学生生活でした。学問は人から与えられるものではなく自分でやるもの、という習性が身についた。学生ストの名目は「大学解体」。権力を持つ支配層を支える学問は拒否するという理屈です。体制に組み込まれた教授たちとは違うことをやる、自分たちの学問は自分で作る、というのが当時の学生の気分でした。翌年3月に封鎖は解除されたけど、先生もやる気がなかった。大学院に入った年がまたもやストで、修士論文も廃止。「大学には何も教えてもらってない」と断言できます。特異な時代です。だけど、何でも自分で納得するまで考える、という今のやり方はこの時できました。 ――では、どうやって勉強したのですか 専門に縛られた重厚な本郷キャンパスの雰囲気になじめず、三鷹の下宿から駒場キャンパスにもっぱら行っていました。駒場にはジャンルを飛び越えた自由な雰囲気があったんです。なかでも教養学部の村上泰亮教授が経済、社会、政治学を統合して現代日本を論じていて、共感しました。村上さんを囲む数人の集まりを作り、毎週議論しました。その後、大きく影響を受けた西部邁(すすむ)さんと出会ったのも、ここです。 ――華やかな思い出は 世間では「神田川」の歌が流れ、同棲(どうせい)ブームなどと言われてたけれど、まったく縁がなかった。女子学生は学部全体で数人ですから。女性は「遠くにありて想(おも)うもの」です。はやっていた合同ハイキングにもダンスパーティーにも関心がなかった。なにしろ小説「罪と罰」のラスコーリニコフのような徹底したネクラな生活に憧れていたから。青春時代になにやってたんだろうね。でも大学生って、堂々と貧しく汚く、落ちこぼれられる特権的な身分ですよ。今の学生にそんな感覚はないでしょうが。(聞き手・織井優佳) (人生の贈りもの)佐伯啓思(63):3(朝日新聞) ■アウトサイダーになりたかった ――幼い日の思い出は おやじは大学の教師でした。しつけは厳しく、口答えすれば、いきなり「ばかやろう!」と殴られた。でも、昔の親ってそんなもの。遊びに行ったよその家でつい壁に落書きし、その家の人が言ってきた時は、半日納屋に閉じ込められました。父は兵隊に2度行って結婚が遅く、一人っ子の僕は年を取ってからの子ども。女学校で教えていた母は良妻賢母の典型のような女性でした。父は中国地方の山の中から出てきて苦学したようです。戦争が終わり、2人とも平和に普通の生活が送れることを大事にして、日々の暮らしをきちっと組み立てるのに関心があった。戦後の一般的な日本家庭でしょう。 ――どんな少年でしたか 普通の子ですよ。成績はまあまあ。幼稚園から中学まで奈良学芸大学(現奈良教育大)の付属にのんびり通い、高校は奈良女子大付属。小学生の頃は、大半の子と同じように長嶋茂雄に憧れる野球少年でした。学校が終わると友達と山へ行ったり、川でザリガニを捕ったり。地域というものがまだあったんです。ただ「まとまろう」とか「学級委員選挙」とかは嫌だった。「みんなで」というのがどうも性に合わない。その頃から「戦後民主主義」に違和感があったんでしょうね。 ――三つ子の魂……ですね 中学3年ごろから「外れた人生」に憧れ始めた。荒くれた、すねた人生を送りたい、と。優等生より、排除され、屈折したアウトサイダーに心ひかれた。物事を斜めから見て世に馴染(なじ)まず、オーソドックスから距離を置くことに憧れる。なのに、自分はこの程度のことしかできない。その気持ちは今も続いている。社会科学をやっている理由はこれなのかもしれません。アウトサイダーがいるから本流が見える。「保守」が何を守るのかが分かる。 ――影響を受けた本は 国語と社会が苦手で、昔は本を読むのも嫌いでした。しかし、高校入学前の春休みに「ジャン・クリストフ」を読んだ。初めてのまともな文学で、悲劇的な苦境を乗り越え、人生を切り開くところに感動した。続いて「チボー家の人々」、ドストエフスキーなど“デカい文学”を次々読みました。 ――重厚な青春ですね 家は奈良市の北の外れ、高校は南の外れだったので、学校帰りに寺や公園に寄り道した。石畳と土塀の道が好きでした。万葉集では大伴家持。名家だった大伴氏は“近代的”な藤原氏に敗れていった。昔からそういうのが好きだったのかもしれません。奈良は京都より華やかさに欠け、「取り残され感」が強い。最初からあきらめたところがあり、どこか哀愁が漂う。この郷土性は、人格形成に少し影響した気がします。(聞き手・織井優佳) (人生の贈りもの)佐伯啓思(63):4(朝日新聞) ■知恵ある生き方 学生に示したい ――学ぶ側から教える側に変わっても、18歳の時から居場所はずっと大学ですね 20代は何をやりたいか定まらず、普通に就職できる気もしなかった。司書でもしながら、子どものころ好きだった推理小説を書くかと漠然と思っていた。29歳で広島修道大学の教員公募に引っかかって助かりました。その2年後に移った滋賀大に15年いて、1994年からは京都大です。 ――今の大学をどう思いますか 当時とはまったく違います。僕にとって大学は、「教わる」ところではなかった。でも、ゼミ生でもないのに出入りしていた東京大駒場キャンパスの研究室で、(評論家の)西部邁(すすむ)さんに出会いました。西部さんは、60年安保を率いた全学連(全日本学生自治会総連合)の中心人物で、当時30代前半。僕が25歳。師というより偉い兄貴分という感じでした。彼自身が「経済学を一から批判する」と猛勉強していた時で、一緒に本を読み、おでんや焼き鳥をつつきながら毎週朝の3時、4時まで話し込んだ。「こんなすごい人がいるんか!」と圧倒され、学問する意味を教えられた。 ただ本を読んでも何の意味もない。その内容を経験の中で確認する“往復運動”が大事なんです。例えば、「関西から来た友人と割り勘で食事した」などと言うと怒られる。上京に費やした負担を勘案しないコミュニケーションは貨幣論的にダメ、というわけです。「知識は生き方や人間関係そのもの」で「学問は生き方の支えになる」と初めて実感しました。 ――そういう出会いが、いまは期待できませんか いま大学は就職斡旋(あっせん)所になってしまった。経営体として自立しろと言われれば、学生は「お客さん」。教員の仕事は教育ではなく、手取り足取り指導して早く就職口を世話することです。そのうえで研究機関でもあろうとすれば、流行を意識し、世の中に役立つ即効性がある研究であるかのようにアピールし、必要なお金を獲得しなければならない。しかし人文系の研究とは、他者と議論しつつ、個人の考えを深めていくもの。1、2年で成果が出るはずがないんです。 ――京都大の定年まであと1年と少し。何をしますか 西洋近代とは何かという長年の関心に区切りを付け、社会科学の土台になる日本的精神の核を取り出したい。でも、時間がないなあ。学生ともちゃんと接しておきたい。知識を媒介にして人格的に触れ合うという、教養を大切にする生き方を示したいんです。教養とは知識ではなく知恵。学んだものが経験を通じて自分の中に蓄積され、いつでも答えを出せる態勢を作ることです。味気なく窮屈な現代社会は暴発寸前。多少の不合理、理不尽をうまく飼いならす知恵が必要だと伝えたい。事なかれ主義に自己中心主義……。「敵」は我々の中にあるんです。(聞き手・織井優佳)=おわり |